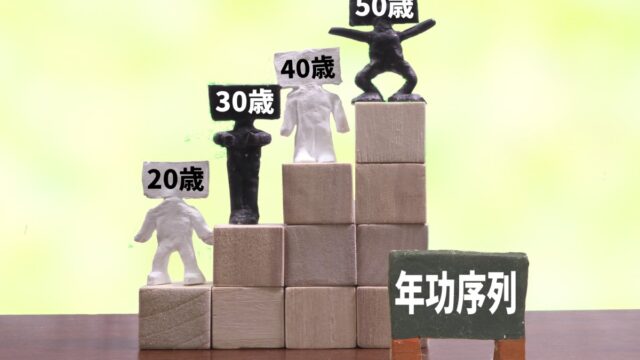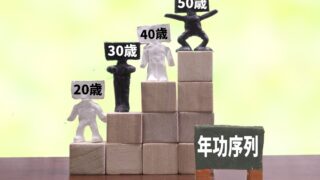ビルメンはプロじゃない?

ある日、トイレ修繕の為にフラッシュバルブを配管から取り外して、分解修理をしている時に、ふらっと様子を見にきた他の係員が言いました。
(*´▽`)「そんなんしなくても、プロに頼めばいいのにー。」
Σ(゚Д゚ノ)ノ「えっ!?(あんたは何を言っているんだっ?)」
(*´▽`)「・・・・・・?」
( -゛-)「あ、はい、こっちでやっとくので、いいですよ・・・。」
ってな、やり取りがありました(笑)
まぁ、通常業務の範囲は請負契約の内容次第で、現場により様々かとは思いますが、同じ様なやり取りがなされる場合も多いのではないでしょうか。
そんな日常の何気ないひと言に、色々と考えさせられたので、私なりに検証してみました。
基本は、仕様書の業務範囲通り
基本的には、オーナー側の会社と自社の取り交わしている、請負契約書の業務仕様書の内容に準じると考えます。
とは言え、実際の業務を行うにあたって、その詳細の業務範囲が的確に明記されているかと言えば、なかなかそうもいかないのが実際かと思います。
古くからの現場であれば、よほど毎年見直しをしていない限り、その様な詳細な内容が明記された仕様書となっているとは思えませんし、新しい現場の場合も、実際の業務に即して受契前から仕様書を詰めることも難しいと言えるでしょう。
現場の立場から考えても、それらの仕様書の大枠を元にして、より実際の設備内容に合わせて、毎年仕様書の内容に盛り込んでいくところかもしれませんが、オーナーを巻き込んでまで、そこまでしていくのは、難しいのは同じかと思います。
そこまで、詳細な記載はそもそもオーナー側は求めておらず、現場の担当者と責任者で決めてくれたらよい。と言った取り扱いが多いのが実際かと思います。

実際は、従来を踏襲した作業が存在する
現場で実際に動く側としては、そう言った細かい決定事項が無数にあり、積み重なっている為、実際どう取り扱えばいいのか、判断に迷う様な状況となってしまうのは、あるあるだと思います。
今回の、トイレ修繕の状況で言えば、分解していた箇所の修理部品は現場に備えてあり、以前から行っている範囲の作業だったので、実際に作業をしていた訳ですが、一部の係員などの中には、ややこしそうな作業は業者に任せてしまったらいい。という意識が強い様で、先の発言となってしまう様です。
当然、現場レベルで対応が不可能な場合は、業者対応となりますが、その流れを知ってしまったが為に、ややこしそうな作業は他の係員に確認したり、取説や完成図などを調べることもせず、「できません。」と安易に答える事に、ビルメンの素人化を感じてしまうのは、以前どこかの記事で書いたようにも思います。
まぁ、特定の係員のグチを言っていても始まらないので控えますが(笑)
ただ、この場合でも、どこまで現場の責任で対応するのかなどは、明確に分けることができないのも事実で、その時の責任者の判断次第な部分があるのも確かです。
また「そんなん聞いてない。」「教えて貰っていない。」「やったことないんで。」と言った、一見不誠実な反応と思える係員の言い分も一理あったりして、完全に否定できるものでもありません。
名もなき作業
家庭内での中でも、「名もなき家事」という言葉がありますが、ビルメンでも「名もなき業務」に近いものがあり、わざわざマニュアル化するのか?といった内容の部分で、新規配属者が失敗して、そんな勘違いがあるのか、などと思わされる事が起こったりします。
極論、教える側の説明不足と言わざるを得ませんが、30年現場にいる係員と、新規配属者の感じ方が違うのはもちろんで、その年数と慣れが故に、気付きようも無い状況が起きるとも言えるのかもしれません。
その逆で、長年あまり深く考えずに行っている作業の中にも、新規配属者の「これ、必要ですか?」と言う何気ないひと言で、実際に検討すると「確かに、改善の余地があるかも。」と効率化や改善に至る場合もあったりします。
「先輩のいう事だから黙って聞く。」なんて言い分は、いまどき流行らないでしょうし、老害などと陰口を叩かれない様に、聞く力や柔軟性を失わずにいたいものです。
まぁ最近で言うと、年下の係員の方が無駄に横柄だったり口が悪くて、年上の責任者などの方がパワハラと言われない様に気を遣いながら、やり取りをしているなどと言った状況もあったりして、チグハグな光景だと感じたりもしています(^^;)
責任者にしてみれば、人材不足で高いとは言えない給与の中、下手に叱責してすぐに辞められても困ると思っている場合も多い様な気がします。
その上で、現場責任者の方針に従う
最終的に、対応が不明な事案については、責任者に判断を委ねるのは、当然の流れですが、全てにおいて判断を仰ぐというのも考えもので、一旦、その状況を見た上で、自分で考えてみたかと、疑問に思う対応を行う係員が多いのも最近の印象です。
ホウレンソウが大切なのはもちろんで、いまとなっては当たり前の様に行われているかとは思いますが、昔のビルメンはその日の作業を作業者で勝手に選んで勝手にどこかへ行って作業をしている何て状況も珍しくなく、何なら、責任者が気に入らないからと、指示された作業は敢えて避けて、作業を行っている係員が居た。と言った昔話を耳にする事さえありました。
これは極端な例ですが、責任者と係員のコミュニケーションは、やはり大切で、それなりに意思の疎通ができていると思っていても、自分が思うほど十分でなかった時期は、事故事案が頻繁に起こるなどの問題があった頃も経験しています。
現場責任者は、その方針を明確にする
私自身が資質的に、コミュ障が入っている為(笑)、口を酸っぱくして繰り返し指示をするのを嫌って、「これくらい今更、言わなくてもわかるだろう。」といった対応をした為に、先の事故事案が頻発していたとも言えるかもしれません。
また、係員が疑問に思っている部分に気付きにくく、それが故に十分なアドバイスを適切に行えていないといった問題もあるかもしれません。
少し説明すれば理解してくれる係員に比べ、資格取得をサボっている様な係員は、やはり基礎的な部分についての理解が乏しく、作業手順についても話が伝わりにくく、だから資格取得を最低限でもしないから・・・。と、関連付けてしまったりもしてしまいます。
まぁ、その方針や指示を明確にするのは、もちろんですが、かと言って、全てにおいてそれを明記し、周知するのも理想的ですが、思い通りにいかないのも現実で、「何で言っている通りにしないんだ?」などと、疑問に思ったりする事も多々あったりします(笑)

良かれと思って行う作業の危険性
通常業務の中には、オーナー側の一般社員などの立場の方から、「〇〇をお願いします。」と何気なく業務外作業を頼まれることもあるかと思います。
係員側も特に難しい業務でなかったり、断るのが苦手な人が電話を受けていた場合に、比較的気軽に「まぁ、今回はこれくらいいいだろう。」と引き受けてしまったりするものです。
結局、そういった場合に、次に同じ様な事案があった場合に、「この間、やってくれたから。」と、頼む側は当然の様に頼んできますし、この2回目の状況で「業務外なので、できません。」と返答しようものなら、「以前は、やってくれた。」と言った反応になるのは当然の流れとなります。
この様な状況が、オーナー側との信用問題に係わってくる可能性があるのは、言うまでもありませんが、仕様外の作業を現場判断で行っていた場合に、破損等の事故事案になり会社に報告するなどの必要が出てきた場合は、当然事故原因を追究されることはもちろん、「そもそもなぜそんな作業をやっているんだ。」と余計な叱責を受ける事になってしまう、というのはよくある状況だったりします。
結論、プロなんで業務と割り切る
ビルメンも、お金を頂いて業務をしている以上、プロ以外のなにものでもありませんが、業務内容に応じて、専門業者や外注に依頼するのは、当然の事かと思います。
係員ごとに、資格取得の状況が違うのはもちろんですし、それに伴い得意な分野が違うのもあるかと思います。
現場規模によるかもしれませんが、大きな現場では不得意な部分については、係員同士で補完しあい協力しながら業務にあたる事も可能ですし、より良い仕事でオーナー側の信頼を得ていくのが、結局、自分たちの現場を良くしていく事にも繋がるのは間違いないでしょう。
一度、信頼を失うと、今までの信頼が一気に崩れると言いますが、誠実に業務に取り組んでいる限り、よっぽどの事案がない限り、信頼がゼロまで失墜するまでの状況は中々ないのではないかと、私は考えています。
甘い考えかもしれませんが、「楽に効率的に仕事をして、それなりの信頼を得る。」なんて選択肢がそもそもない以上、「誠実に、業務に向き合う。」ことを日々繰り返していくしかないかと思います。
ただ、それを現場全体で行うのが、非常に難しいと言う問題が一番、大きかったりもしますねw